Event report
2025.11.26
ふらっと立ち寄る、旅先のミュージアムショップ
まるで旅先でふらりと入ったミュージアムショップのように、棚の向こうから「今」を生きる手仕事が語りかけてくるようにしたい。FabCafe Nagoyaで2025年9月26日(金)〜10月14日まで開催された 「like a museum shop」は、買うだけではなく、風土に触れ、語ることで、文化を<手で持ち帰る>ための実験ショップです。
能登、瀬戸、瀬戸内は、いずれも海と風土に根ざした文化を持つ地域です。カフェの一角に並ぶのは、今を生きる私たちのための工芸品です。毎日手が伸びてしまうような、暮らしに静かに馴染んでいく作品や道具が並びました。
出品されたもの
能登:海と山に面した土地からは、漆器や味噌、昆布など、生活のそばで続く手仕事が並びました。角藤漆器店による椿皿や豆皿、輪島の谷川醸造による発酵調味料など日々の食卓を支える品々に加え、瓦の新たな可能性を探る〈GAWARA〉の瓦箸置きや、防災をテーマにした〈饅頭防災〉など、若い作り手たちの挑戦も。
瀬戸:焼き物の町からは、うつわやすり鉢など、日々の食卓を支える道具が登場。〈眞窯(しんがま)〉や〈王子窯〉の器が並び、地元アートスタジオ〈タネリスタジオ〉の作品も加わることで、「伝統と現代」が混ざり合う作品が並びます。
瀬戸内:香川や岡山の沿岸部からは、漆うちわや木工品、大漁旗をリメイクしたテキスタイルなど、風土と暮らしを映すアイテムが集まりました。現在の暮らしにも取り入れやすい漆器や木工などの作品に加えて、香川発のお茶ブランド〈SABI〉が手がける日本茶も登場。
オープニングの夜、「文化をあたためる」パーティー
2025年9月26日に、展示の幕開けを祝うオープニングイベント がFabCafe Nagoyaで開かれました。能登・瀬戸・瀬戸内の作り手や関係者が集まり、作品や道具を手に取り、会話の温度を通して<風土の違い>と<共通点>を体験しました。
その象徴となったのが、香川の茶ブランド SABI によるオリジナルティーカクテルです。瀬戸内のお茶と能登の地酒を、愛知県瀬戸市で作られるやきものの総称である<瀬戸もの>の祖と言われる王子窯の器でいただく。三つの地域が「香り・味・触感」で交わる体験は、まさに<風土のマリアージュ>と言えます。

SABIは、香川県高松市を拠点に「日本茶を気軽に楽しめるティースタンド」として始まったベンチャーです。当初は「茶日」としてポップアップ形式から活動を始め、現在はスタンド&ギャラリー併設の空間で、お茶の可能性をカジュアルに・クリエイティブに拡張しています。
お茶の種類を選ぶと、SABIが用意した3種のお茶(浅蒸し煎茶/浅煎りほうじ茶/京番茶)に、オススメの能登のお酒を組み合わせてティーカクテルにしてもらえます。
コーヒー/バリスタ出身の背景を持つSABIのメンバーの一人は、茶葉の温度・抽出時間・淹れ方などをロジカルに解析しながら、既存のお茶文化を再解釈しています。
会場では、三つの地域の文化を「味覚」でも感じてもらうために、各地の食材や調味料を中心にした軽食がふるまわれました。塩や味噌、いしる(魚醤)など、能登の風土に根づいた調味料をベースに、金糸瓜(きんしうり)や能登白ねぎなどの伝統野菜を使った小皿料理が並びました。さらに、瀬戸内の柑橘ドレッシングや小豆島オリーブの香りを添えて、土地の味が交わる工夫も。
 能登の料理人にアドバイスいただきながら、FabCafe Nagoyaで考案したレシピが並んだ
能登の料理人にアドバイスいただきながら、FabCafe Nagoyaで考案したレシピが並んだ
クロストーク:「文化は、住むことから始まる?」
展示会場の中央に置かれた長テーブルを囲みながら、「文化は、住むことから始まる?」をテーマにしたクロストークが行われました。能登、瀬戸、瀬戸内、三つの地域で「土地とともに生きる」実践を続けてきた登壇者が、それぞれの現場で感じていることを率直に語り合いました。
話した人

写真左から(※所属・役職は取材時点のもの)
右から、
森岡 友樹さん(アーティスト/プランナー 企画発起人)
森 美樹さん(うのずくり たまののIJUコンシェルジュ、Like a museum shop 瀬戸内エリア企画協力 ガラス作家)
設楽 陸さん(画家、VRアーティスト、タネリスタジオ代表)
嵩山 大史さん(経済産業省 中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課)
吉澤 潤さん(WHOLE、Like a museum shop 能登エリアセレクトパートナー)
斎藤 健太郎(FabCafe Nagoya 企画発起人)
「違いを並べる」と、風土が立ち上がる
今回の展示「like a museum shop vol.1」は、岡山・玉野で毎年開催されているアートイベント「幻のミュージアムショップ」から着想を得ています。もともと、キュレーターの山田茂さんを中心に始まったこの企画は、作品を展示するのではなく日常にひらくという発想で、多くの地域で共感を生んできました。その思想に共鳴し、企画者の森岡友樹さんとFabCafe Nagoyaの斎藤が、能登・瀬戸・瀬戸内という三つの地域を横断するかたちで発展させたのが今回のプロジェクトです。
最初に話を切り出したのは、企画者の森岡さんでした。
森岡:今回取り上げた、3つのエリアである能登・瀬戸・瀬戸内は、似ているところと違うところがあります。そして、その背後には必ず、風土や文化、歴史の違いがある。並べてみると、その意味が浮かび上がってくるんじゃないかと思ったんです。

今回の展示は、三つの地域の工芸を「比較」ではなく「共演」として並べることを意図していました。「並べる」ことそのものが、風土を語る方法であり、文化を可視化する試みです。
森岡:同じ日本の中でも、土の色、空気の湿り気、人のテンポがまったく違うんです。並べてみて初めて、能登の漆の重みと、瀬戸の磁器の軽やかさが、それぞれに必要な理由を語り出すんですよ。
展示の奥には、「違いを愛でること=風土を尊重すること」という思想が流れていました。

テーブルの高低差を生かし、能登・瀬戸・瀬戸内それぞれのエリアに作品や道具を並べた
能登の<いま>を伝える、手のひらの温度
話題は自然と、能登の現状へと移りました。2024年の地震から約1年半が経ったいまも、まちは復旧の途中にあります。斎藤は、この夏、写真家・稲田匡孝さんと能登を訪れ、地域で活動する作り手や事業者、そして風土とともに息づく日常を撮影しました。「復興」という言葉から連想される整った光景とは違い、そこに日常を取り戻そうとする、静かな営みが広がっていたと語ります。
斎藤:1年8か月も経てば落ち着いているだろうと思って現地に行ったら、そんなことは全然なくて。僕が回ったエリアでは、ようやく生活が始まるという段階でした。建物はまだ修理中のところも多いけれど、手を動かしている人の姿が本当に多かったです。みなさん、次の春に向けて準備しているという様子で、その手の動きが何より力強く見えました。
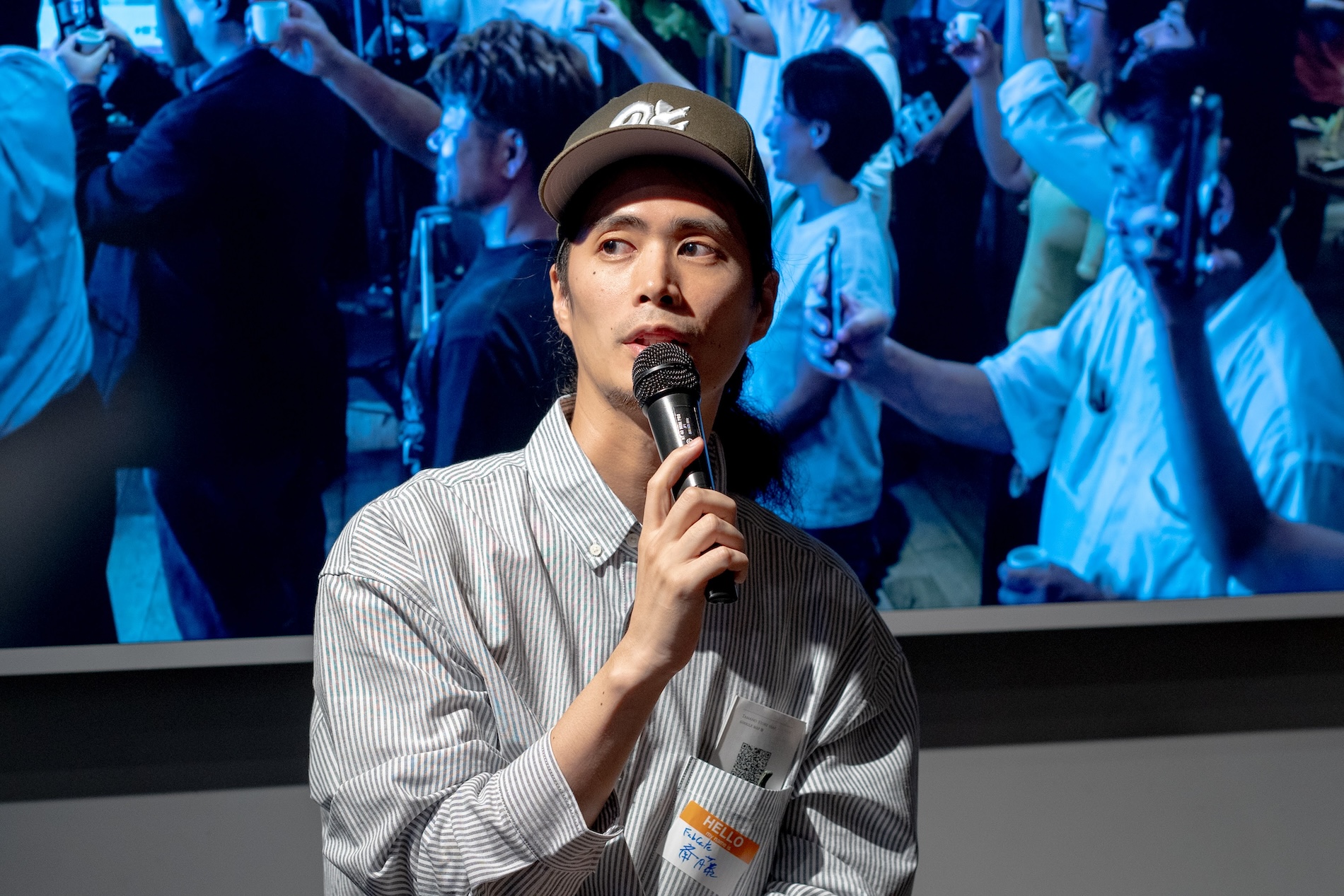
現地で撮影された写真のいくつかは、今回の展示にも反映されました。斎藤と写真家・稲田匡孝さんが訪れた珠洲では、珠洲や奥能登のこれからを考える「奥能登アーカイブ」の拠点として設立されスズレコードセンターで出会った西海一紗さんや、運営スタッフとして地域を支える若者たちが印象的だったといいます。
また、あるお寺では、地域のおじいさん、おばあさんに囲まれながら一緒に水引づくりを体験し、手を動かしながらランチを共にし、そのままカラオケまで行ったそうです。
斎藤:誰かに応援の声をかけるよりも、そこに行って、同じ時間を過ごすことのほうがずっと大事だと感じました。その空気を、今回の展示でも伝えたかったんです。
能登からは、漆器、味噌、昆布、能登瓦を使った小物など、暮らしの根にある工芸がセレクトされています。能登エリアのセレクトを担当した吉澤さんは、自身が手がける瓦ブランド「GAWARA」について、こう語りました。
吉澤:僕は能登の南、小松出身なんですが、子どものころは瓦屋根があまり好きではありませんでした。正直に言えば、古臭いと思っていました。でも、職人さんの話を聞いたときに、地域によって色が違うこと、それがその土地で採れる釉薬の成分の違いによるものであることを知って、一気に見方が変わりました。

瓦づくりは、まさに風土の産物です。北の能登ではマンガンを多く含む黒、南の小松では鉄分を多く含む赤。その土地の土が、そのまま屋根の色になるといいます。震災後、被害を受けながらも能登の家にはあの黒瓦でなくてはならない、まだ使えるあの瓦をどうにかできないかという現地の方の声に背中を押され、ブランドを続けてきたそうです。
吉澤:44歳を超えて初めて、自分の故郷の屋根の理由を知ったんです。現地の人は、語る前に続けているんです。だから僕たち外の人間は、それを見て、触れて、感じて、自分たちに何ができるのかを考える番なんだと思います。
「住む」から始まる文化。瀬戸内で育まれる暮らしの風景
話題は、岡山・玉野の「幻のミュージアムショップ」に移ります。移住支援や空き家の紹介を続ける森美樹さんは、15年以上にわたる地域との関わりを語りました。
森:私が17年前に移住したころは、商店街のアーケードが取り壊されていく最中で、コーヒーを飲める場所もありませんでした。でも少しずつ仲間が増えて、今では駅周辺を中心に30軒以上の新しいお店ができています。
森さんが移住支援に関わってきた15年で、玉野市には約240人が移り住みました。驚くべきは、その「離脱率の低さ」です。
森:出ていく人が少なくて、出ていっても遊びにきてくれる人が多いです。それは、「楽しい」を自分たちで作っているからだと思います。便利ではないけれど、楽しい。それがこの町の文化なんです。

瀬戸の作家支援にも関わっている森岡さんも頷きながら言葉を重ねます。森さんは、地域の誰かが「やりたい」と声を上げたときに、「じゃあ、やってみようよ」と背中を押すようにしているそうです。
森岡:結局、自分たちで楽しみをつくることが文化になるんですよね。誰かにやらされるんじゃなくて、自分の暮らしを自分で面白くする。それが町を変える力になると思います。みんなが頑張らなきゃと気負うのではなくて、ちょっと困っている人がいたら手を貸す。でもべったりはしない。その投げっぱなしの優しさが心地いいんです。
地域づくりという言葉の裏にある、柔らかな関係性。それが、玉野のまちの生きやすさを生み出しているのかもしれません。
郊外のアートが息づく場所、瀬戸の実験
一方、愛知・瀬戸で活動する設楽陸さんは、アーティストとして、そして場を運営する立場から語ります。
設楽:「瀬戸って、アーティストが住むにはちょうどいいんです。自然が近くて、街の人の距離感もほどよくて。生活と制作が、無理なく地続きでできる場所なんですよ」
瀬戸では、古いビルや商店を改装して、複数のアーティストが共同で使っているそうです。広々とした空間を分け合い、展覧会を開いたり、地域の人を招いたりしながら、日常と創作がゆるやかに行き来する時間が流れています。

設楽:都市部のように作品を売るために作るという緊張感が少なくて、もう少し呼吸するように活動できる。商店街のおじいちゃんも若いアーティストも、みんな同じ空気の中で暮らしているんです。いい意味で、人が多様すぎて、誰も浮かない。みんなが混ざっていて、アートが日常の中で呼吸しているんです。
瀬戸は、伝統産業と現代アートが混ざり合う町です。古くから続く陶芸の文化に、若い世代の実験的な創作が重なり、「つくること」が特別ではなく、日常の延長にあるように感じられます。その言葉のとおり、瀬戸には作品と生活を分ける境界がほとんどありません。窯元の隣でライブが行われたり、陶片が街のベンチに使われていたりと、暮らしのあらゆる場所に創造の痕跡が息づいています。
文化を運ぶルート「道」を考える
終盤、話題は「道」に広がりました。森岡さんが口にしたのは、北前船の話です。
森岡:道を考えると、文化の流れが見えてくるんです。能登の工芸も、うどんの文化も、北前船の交易ルートとともに広がっていった。風土をつなぐのはモノだけじゃなく、人の往来なんですよね。
吉澤:能登の黒い瓦は、もともと島根の赤瓦から伝わったとも言われています。北前船の時代には、人も技術も行き来していた。だから、地域固有といっても、実は混ざり合っているんです。
「道」というキーワードが、過去と現在、そして未来をつなぐ比喩として立ち上がりました。ここでマイクを握ったのが、中部経済産業局の嵩山大史さんです。能登をはじめ、各地の中小事業者やクリエイティブ産業を支援する立場から、行政が文化活動にどう関わるかを語ってくださいました。
嵩山:文化的な活動は経済活動ではないと分けて考えられがちですが、実際に現場を訪れると、その境界はすでに曖昧になっています。能登の工芸や食文化を支えるのは、地域の“手を動かす力”であり、それが結果的に地域経済の基盤にもなっているんです。

嵩山さんは、被災後の能登で出会った人々の姿を振り返ります。
嵩山:工房や店舗が被害を受けた後も、「とにかく仕事を止めない」と現場に戻って作業を続ける方々がたくさんいました。その止めない力が、実は復興の土台をつくっている。私たち行政ができるのは、そうした人の動きを見える化して、次の人へとつなげていくことだと思っています。文化や産業を守るというより、伴走するという感覚に近いです。現場で生まれる小さな取り組みが、気づけば次の人を動かしている。その連鎖をどう支えるかが、これからの行政の役割ではないでしょうか。
「止めない力」―能登を支えたもうひとつの現場

「止めないことが支援になる」。その姿を伝えるために、今回の展示では、もうひとつの「現場」を記録した写真シリーズが紹介されています。
会場の一角には、能登で続く燃料供給の現場を撮影した写真が並びます。それは作る人の裏側で、暮らしを動かす人々の姿を記録したもの。派手な復興のシーンではなく、日々の営みを淡々と続ける人たちの静かな時間が切り取られています。「誰かに気づかれなくても、誰かが必ず必要としている仕事がある」。そんな当たり前の尊さを写真が伝えてくれました。
「文化は、住むことから始まる?」という問いは、実はどう続けていくかという問いでもあります。作る人、支える人、つなぐ人。それぞれの立場で道をつくる人たちが交わり、今回の展示とトークは、新しい「文化の循環」を描き出しました。
文化は、誰かが決めた道を歩くことではなく、自分たちで道をつくりながら、進んでいくこと。そんな小さな実践の連なりが、この展示を通して見えてきたことなのかもしれません。
出展プロジェクト

<能登>
GAWARA(小松市)
能登とととプロジェクト(かほく市)
角藤漆器店(輪島市)
杉本君平 木桶職人/大工(小松市)
大脇昆布 おぼろ昆布製造販売(能登町)
谷川醸造 醤油・味噌製造販売(輪島市)
<瀬戸>
眞窯(瀬戸染付のうつわなど)
王子窯(うつわ、すり鉢、湯呑み)
瀬戸の現代美術(タネリスタジオ)
<瀬戸内>
さざなみ漆器(うちわと漆芸)
暮殻 – kurekara -(木工)
琴平 染匠吉野屋(大漁旗など)
SABI(香川の日本茶ティーバッグ・お茶を使ったオリジナルドリンク)
幻のミュージアムショップ セレクト品
※岡山県玉野市宇野のアーティストや作家による作品
執筆・撮影:宮崎真衣(ロフトワーク)
-
宮崎 真衣
株式会社ロフトワーク 広報
広報の理論と実践を「Mie Institute of Communication」で学んだ後、アートやIT企業の広報・企画職などを経てロフトワークに入社。さまざまな場面でわきおこるコミュニケーションを、組織だけではなく暮らしや地域に還元していくために、cooperative(協同組合)やcollective(拘束力を持たない緩やかなネットワーク)に参画しながら学びを深めている。
広報の理論と実践を「Mie Institute of Communication」で学んだ後、アートやIT企業の広報・企画職などを経てロフトワークに入社。さまざまな場面でわきおこるコミュニケーションを、組織だけではなく暮らしや地域に還元していくために、cooperative(協同組合)やcollective(拘束力を持たない緩やかなネットワーク)に参画しながら学びを深めている。










 「GAWARA(ガワラ)」は、石川県小松市から始まった瓦の再発見プロジェクト。名前の由来は、瓦が笑うと書いて「瓦笑(がわら)」
「GAWARA(ガワラ)」は、石川県小松市から始まった瓦の再発見プロジェクト。名前の由来は、瓦が笑うと書いて「瓦笑(がわら)」



