Event report
2025.11.26
FabCafe編集部
2025年10月31日、FabCafe Nagoyaにて、第3回「Nagoya After School Lounge」が開催されました。今回のテーマは、「ちいきで学ぶ、ちいきと学ぶ」。
イベント前半は、特別ゲストとして岐阜県飛騨市を拠点に「教育や学びを通じて持続可能な社会をつくる」活動を展開する株式会社Edo 盤所杏子さんが登壇。地域を舞台にした学びの実践や挑戦についてお話ししていただきました。後半は、” ちいきで学ぶ、ちいきと遊ぶ ”をテーマに、幼少期のエピソードを通して学びの対話が繰り広げられました。
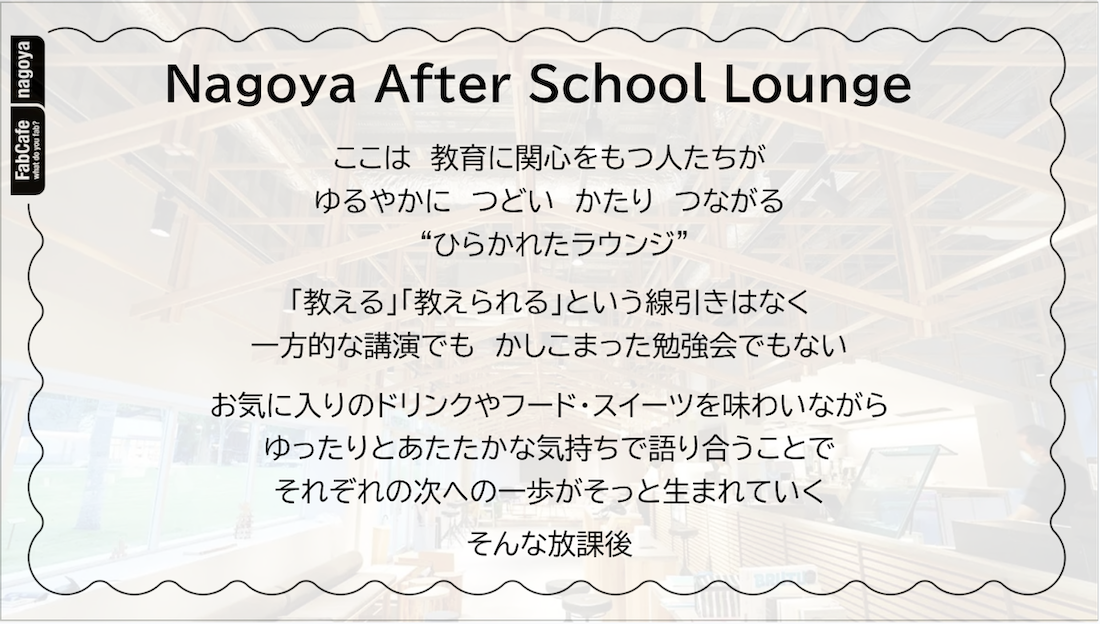
「Nagoya After School Lounge」
教育に関心をもつ仲間と、ゆるやかに交わる“対話と創造の場”。教育に関わる多彩なゲストをお迎えしながら、「気づき」と「つながり」が生まれる、ちょっと特別な放課後。
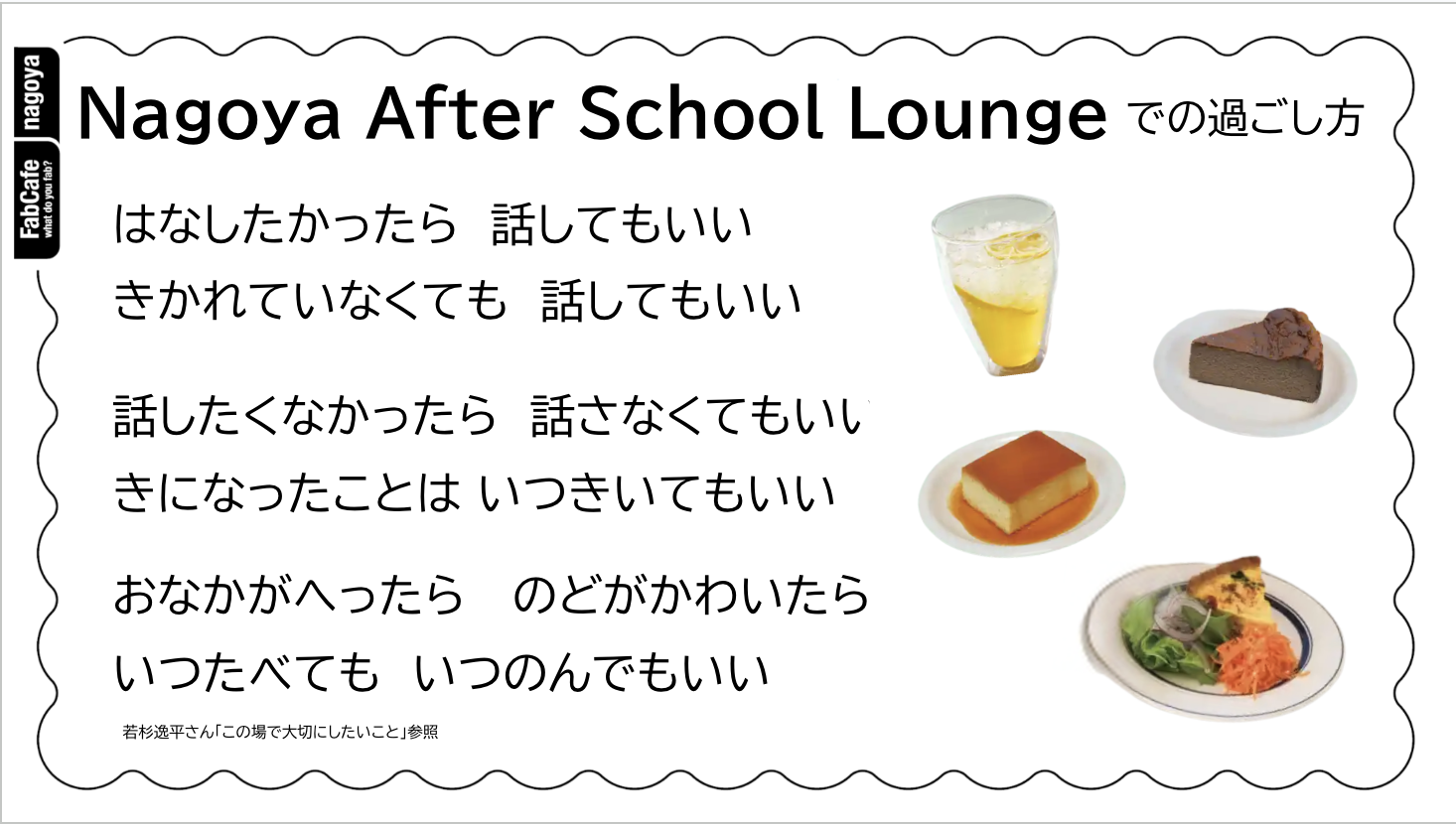
「教える」「教えられる」といった一方的な講演会でも、気合いの入った勉強会でもない。互いに気づき学び合い、次への一歩を共に生み出し合う。そんなゆるやかであたたかな場。
第1回目 正解探しを手放した先にある、新しい教育の対話の場
第2回目 学びをプレイフルに!〜遊び心がひらく、新しい教育のかたち〜
あなたはどっち?
Nagoya After School Lounge は毎回、参加者同士が対話しやすいように、アイスブレイクから始まります。
今回のアイスブレイクは、会場をめいいっぱい使用し、身体ごと移動するアンケート。
2択の問いかけに対し、それぞれの当てはまる属性に大移動します。もちろん真ん中もOK。
今日はどんな方が参加しているのかが一目でわかります。
アンケート結果をほんの少しお見せします。
教員の方 or そうでない方… 半分の方?
意外にも教員の方の参加者は少ない。なんと真ん中の人もいました。
多様な属性の方にご参加いただいています
参加者は平成生まれ or 昭和生まれ?
下は16歳の高校2年生から。
教員や経営者の方と、高校生が同じテーマで対話する場所になりました。
第3回のテーマ「ちいきで学ぶ、ちいきと学ぶ」
特別ゲストとして、岐阜県飛騨市を拠点に「教育や学びを通じて持続可能な社会をつくる」活動を展開する株式会社Edo 盤所 杏子さんにお越しいただきました。
公教育の底上げとともに、地域の場作りにも
人口減少が進む地域においても、「ここで暮らしたい」と思う人が幸せに暮らし続けられる──そんな未来をつくるためには、地域の中で人・もの・お金が循環し、多様な人々が共通の目標を掲げながら連携し、協働し、地域という大きな“歯車”がスムーズに回る仕組みが欠かせません。
盤所さんは、その仕組みを支える重要な要素のひとつが「教育」であり、Edoはまさにこの教育を軸に地域づくりに取り組んでいると語ります。

地域で学んだ経験を振り返る
対談の1つ目のテーマは「自分が子どものころ 地域で/地域と 学んだと感じていること」。幼少期の思い出を手がかりに、地域と関わる中で得た学びをお話しいただきました。
遊びのなかから生まれる学びやエピソードが飛び交う中で、こんなコメントもありました。
「必ずしもポジティブな経験だけが学びではなかった。」
ある時、私の家の裏山に生えていた木の実が気になって取ってみた時に、地域の方に「そこの木の実は誰々さんが管理してるから勝手に取るな!」と怒られたことがあって。友達といた私は、逃げました(笑)。この木の実って誰かのものなの?自然のものじゃないの?神様がつくったんじゃないの?って。そこから、社会の見えないところで誰かが支配しているとか、管理している、統率しているっていうことの不思議さや理不尽さにちょっと興味をもち始めました。疑問をもつということも学びだなと、ちょっと今思い出して。
自分の好奇心に純粋にしたがって生きている時に、急に降ってくる問いは、刺激的、衝撃的な出来事で、違う視点が生まれる。
地域のコミュニティのなかに、子供達の遊び場がある状態は、地域の大人と子供の交わりを通して、そこが自然と学びの場を形成するということを、過去のエピソードを振り返り見えてきました。
地域と学ぶ上で大切なこと、必要なこととは?
対談の2つ目のテーマは「地域とまなぶ、地域でまなぶうえで大切なこと・必要なこととは?」。
「企業」「地域住民」「教員」「学校」「文化」といった小テーマのなかから、同じテーマで話したい人たちとグループになり、地域と学びの関係性について対話を行いました。

地域住民グループ
幼稚園、保育園のお祭りを地域のお祭りに変えたことで、移住してくれる人も参加しやすくなったという事例が紹介されました。また、あらゆる関係性がお金のやりとりありきになってしまっている点に対して、あえてマネタイズしすぎないことが、参加者同士で話のきっかけや感謝のやりとりを生み、地域が盛り上がるのではないかという意見が出てきました。
物事がお金を介して行われるサービス化に移っていくことで、発生する弊害もある。
本当に自分がこれをやってあげたい。こういうことで困っているから助けて欲しい。そここあらうまれる新たな関係性や学びが大切なのでは?という意見がでました。
教員グループ
教員が、職員室という閉鎖的な空間から外に出ることが大事なのでは?
そして、生徒も連れてきて一緒に参加し、このような場で多様な人とつながるできたらいいなという意見が出てきました。
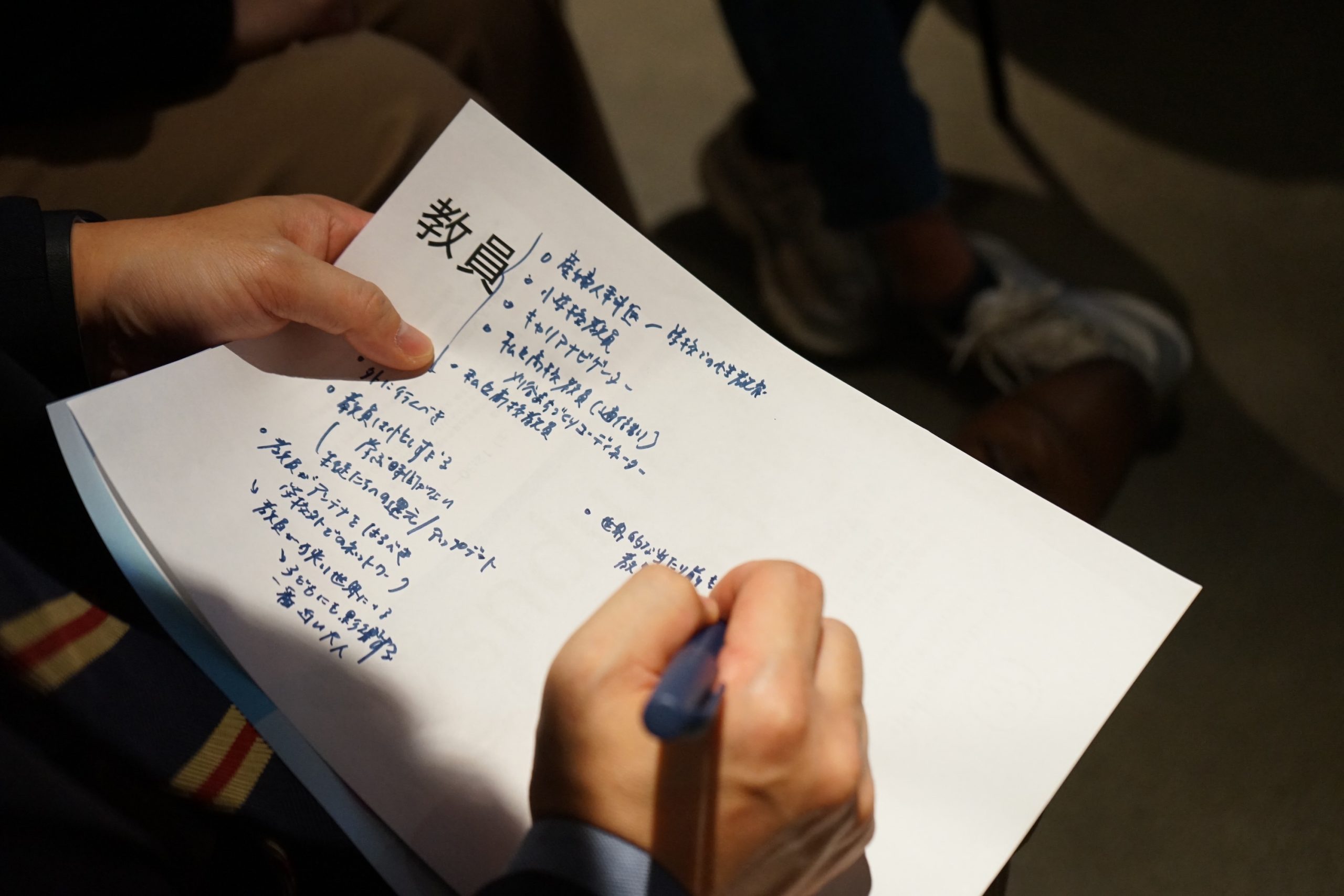
実際に、先生と一緒に今回参加してくださった「先生の教え子」である学生さんからは。
今は、大人と子供の境界線が曖昧になっている。だからこそ、一歩前を走っている大人や、見守ってもらえる、サポートしてくれる人が「大人」。大人が作る環境に子供は影響を受けやすいから、周りでサポートしてくれる大人がどういう人かが重要だと思うと。

文化グループ
「文化と文化が重なる時に違和感を感じる。でもだからといって、それがダメなのではなく、だからこそ重なる部分の輪っかを広げていくことが大事ではないか?」と話してくださった。
みんな同じだと考えると、違うばかりが際立ってしまう、目立ってしまうけど、元々違っていると、その違いが面白い。共通するものが生まれ、見つかると、うれしいと、ご自分の経験を交えて語られました。
今回の対話を通じて、「教育に関心ある人や大人は、つい学びを設計しようとしてしまうのかも」という気づきを得ました。
同じ場に集い、1つのテーマに対して一緒に対話することから自然と生まれる学び。
同じコミュニティで過ごすなかで個人の想いや考えが交わるところに学びがあるのかもしれないと思いました。
地域があるということは、学びの場があるということ。ここにどう大人が関わっていくか、また地域と呼べる場所をどうこれから作っていくかが大切なのではないかと改めて考える時間になりました。
FabCafe Nagoya では、教育をテーマにした学校・学生連携や、子ども向けプログラムの開発・実施をしています。また、SEL(Social Emotional Learning)をベースにしたソーシャルスキル・エモーショナルスキルの研修やプログラム設計、企画のご相談も可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
-
FabCafe編集部
FabCafe PRチームを中心に作成した記事です。
この記事に関するご意見やご感想は、ぜひお気軽にこちらからお寄せください。
→ お問い合わせフォームFabCafe PRチームを中心に作成した記事です。
この記事に関するご意見やご感想は、ぜひお気軽にこちらからお寄せください。
→ お問い合わせフォーム
