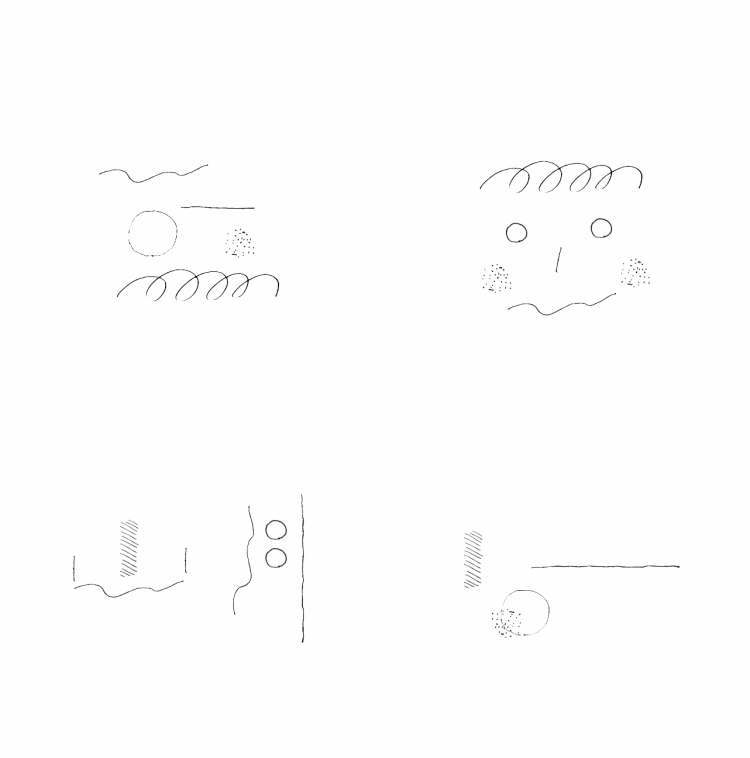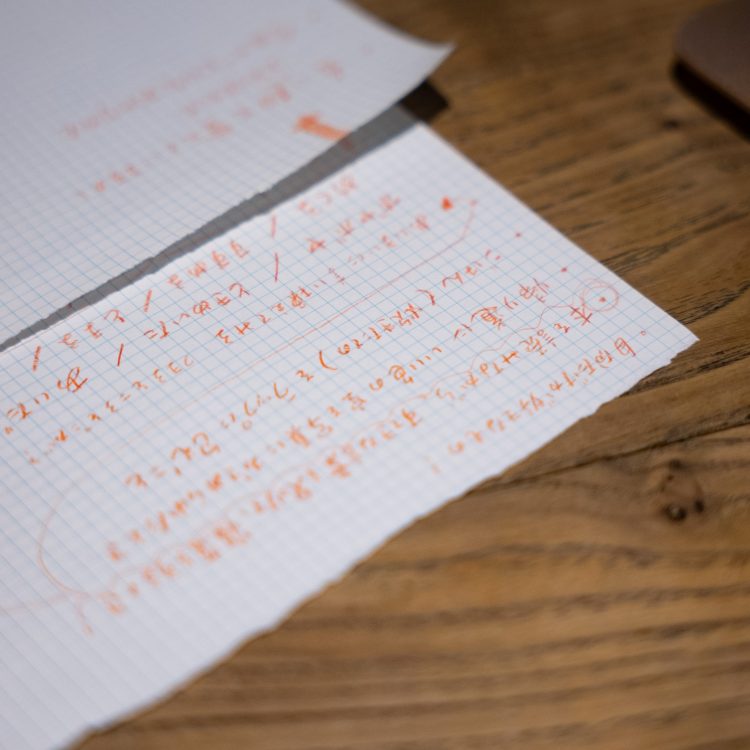Event report
2025.1.18
山月 智浩
FabCafe Kyoto ディレクター
株式会社ロフトワークが運営する「FabCafe Kyoto」は、大阪・鶴見緑地に開設された日本初のコミュニティ型こどもホスピス「TSURUMIこどもホスピス」(運営:公益社団法人こどものホスピスプロジェクト)との共同企画として、2023年よりデジタル工作機器を活用したワークショップを実施しています。「つくる」体験を通じて、身体的・精神的にさまざまな事情を持つ子どもたちの「できた!」を後押しすることを目指します。第2回となる本年は、施設を利用する中高生を主対象としてシルクスクリーンのプログラムを開催しました。
FabCafe Kyotoがどのような協働のもと、つくる手段へのアクセス経路を開くことに挑戦しているのか、また、何かを形づくることがいかに「人が深く生きること」に寄与しうるのか、昨年度に続くその実践の道のりをレポートします。
2016年に開設した日本初のコミュニティ型こどもホスピス「TSURUMIこどもホスピス」。小児がんや循環器疾患など、生命を脅かす病気(Life-threatening conditions=LTC)を抱える子どもたちが、たとえ辛い治療の最中にあっても本来享受すべきその子らしい時間を叶えられる環境づくりを推進しています。現在進行形で病気と戦う子、治療がひと段落したけれど、その辛い経験から自信を喪失してしまう子、またそのきょうだいなど、身体・精神面におけるさまざまな事情によって生活のための選択肢が制限されてしまう子どもたち。私たちは地域に開かれたメイカースペースとして、彼らに対しどのように「つくる」ための手段を開くことができるだろう、そんな問いを発端として、2023年度よりTSURUMIこどもホスピスと共同で、デジタル工作機器を用いたワークショッププログラムを実施しています。

TSURUMIこどもホスピス外観。OsakaMetro長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」から徒歩3分ほどに位置する
初年度に実施したプログラムでは、紙や布、アクリル板などさまざまな素材の切断や刻印加工が可能な「レーザーカッター」を使用。子どもたちの描いた手書きの線をもとに、自分だけの「水たまりの鏡」をつくるワークショップを開催しました。子どもたちが自ら引いた線が、レーザーカッターを通じて鏡の板を切り抜く力へと生まれ変わる不思議に、ホスピスに通うみんなは興味津々。デジタル工作機器を用いた「つくる」体験が、子どもたちの「できた!」を後押しできる可能性を感じることができました。

▶︎レーザーカッターを用いた昨年の実施内容についてはこちら
本年度は、子どもたちの「できた!」の実現に加え、ホスピスが抱える課題にもアプローチ。スタッフである川戸大智さん、青儀祐斗さんとの打ち合わせで伺った「利用する子どもたち同士の関係性の希薄さ」に着目し、個人で完結する内容ではない、子どもたち同士の関わりを促せるようなプログラムを設計することが決まりました。
また、本年FabCafe Kyotoに正式に導入された「デジタルスクリーン製版機」を用いたシルクスクリーンを体験の核とすることも決定。穴の空いた「版」をもとに、上からインクを押し出すことで布や紙などあらゆる物に印刷が施せるシルクスクリーンの楽しさをどうプログラムに織り交ぜられるか、アイデアを出しては試作を繰り返しながら、企画を進めました。
-

アイデアの一部。福笑いのように、幾つかのパーツを組み合わせて自分だけの模様を生み出す案
-

透明な板にシルクスクリーンで雲を印刷。向こう側の景色と組み合わせてみる
-

刷るための言葉を自分の感情から紡いでみる実験。小さな対話型ワークショップを何度も繰り返して企画の骨子を組み立てる
子どもたち同士の関わり合いを促すこと、また、残す・伝えるための印刷技法であるシルクスクリーンを主軸とすること、この2点をもとにFabCafe Kyotoが提案したのは、子どもたちの言葉が建物全体に点在する仕掛けづくり。子どもたちが「誰かへの質問」を施設内の各所に印刷し、施設を利用する他の子どもたちや多様な来訪者が空間を通して彼らの問いかけと出会うことで、ワークショップの場だけに留まらない、継続的・偶発的なコミュニケーションが生み出せないかと考えました。

また、印刷するための言葉を考える「編集」や、他者に届けるための「印刷」のプロセスを、仮設的に「TSURUMIこども出版社」と総括することで、出版社のメンバーとしてひとつの読み物を立ち上げるべく、子どもたちが協働しながら関われる場づくりを目指しました。

シルクスクリーンで制作した出版社の看板。かわいい

当日参加してくれたのは、書くことや作ることに関心のある中高生4名。大学でものづくりを学ぶボランティアメンバーの学生たちとグループになり、一日限りの出版社「TSURUMIこども出版社」のメンバーとして、施設に印刷するための質問を考えます。
大きく2つのプロセスで構成された今回のワークショップ。
質問を考える編集のプロセスでは、「質問のレシピ」を頼りに自分の個人的な体験から言葉を考えます。「あなたが心地よいと思う瞬間を一つ教えてください」「その理由を詳しく書いてください」などの設問に沿って、他者に投げかけるための「問いの素材」を自分の内側から引き出すことを意識しました。「雲を眺めるのが好き」「デッサンしているとき」「AIに絵を描かせているとき」など、出てくるエピソードやその理由からその子の内面が垣間見える瞬間も。それらを単語に分解し、まるでカードゲームのように偶然の力を利用しながら自分の言葉を再構築してみることで、誰でも読む人に想像の余白を与える質問が考えられるプログラム設計を目指しました。
質問に答えることはあっても、自ら誰かへの「問い」を意識的に組み立てる機会は、子どもたちにとってそう多くはありません。あらかじめ決められた正解がなく、言葉を紡ぐことの難しさやうまくいかなさに戸惑う場面も見られましたが、それぞれがその子なりの表現にたどり着くことができました。
質問が形になったら、いよいよ「印刷」の行程です。
登場するのは「デジタルスクリーン製版機」という機械。薄いフィルムに、インクを押し出すための細かい穴を空けることで、任意の図案をあらゆる素材に印刷することが可能になります。
子どもたちの言葉をその場でデータ化し機械に送信。「ウィーーーーン」という音がしばらく続き、わずか2分ほどで、印刷するための「版」ができあがりました。
みんなが考えた質問が一番映える場所はどこだろう?どんな時にこの質問を考えてほしいかな?など、言葉を受け取る人や、言葉が持つ意味と景色の関係性を考えながら、質問を配置する場所を探します。
この日ワークショップに訪れたどの大人よりも施設のことに詳しい彼ら。質問を考えるのに悩んでいたかと思えば、今度は率先して私たちに印刷場所を案内してくれました。誰かが印刷するときには版を持ち合うなど、協力して一つのものを作り上げる風景が自発的に生まれていたことも印象的です。
ものづくりに関する質問はクラフト部屋の窓ガラスに、寝ることに関わる質問は宿泊部屋に、既に施工されていたピクトグラムに合わせて印刷された質問も。どの言葉も、ぴったりの場所に印刷されていました。この日印刷された質問の中から、いくつかを抜粋してご紹介。
 「あなたは、七色以上使って絵を描いた事がありますか」
「あなたは、七色以上使って絵を描いた事がありますか」
 「なぜ発信をするのでしょうか」。TCHに通所しながら広報活動に取り組む高校生の根源的な質問
「なぜ発信をするのでしょうか」。TCHに通所しながら広報活動に取り組む高校生の根源的な質問
 現実とアニメ(フィクション)の境界を問う質問。エレベーターのドアが開いた先、鏡に写った自分の姿と質問が重なる
現実とアニメ(フィクション)の境界を問う質問。エレベーターのドアが開いた先、鏡に写った自分の姿と質問が重なる
 最後に質問の意図や自分の考えを発表
最後に質問の意図や自分の考えを発表
「届くこと」の思いもよらなさを感じてみる
まるで一冊の詩集の中を歩いているように、この日参加したみんなの言葉が、空間のあちらこちらに潜みます。窓を開けて外に出るとき、日のあたる廊下をわたるとき、不意にだれかの言葉と出会う不思議。向こうの景色や、映る人、流れる雨粒のひとつずつ。どの質問も、窓や、窓を取り巻くいくつもの風景と連絡を取り合いながら、そこには思いもよらない意味や空気が生まれていました。

この日生まれた質問たちを、いつ誰が受け取ったか、明確に知る術はないかもしれません。けれど、正解のない、彼らの内側から発された問いかけには、不思議と読者の胸を打つ力があります。それは明日かもしれないし、1年後、10年後かもしれない。
「言葉を誰かに届ける」ことは、その思いもよらなさを受け止め合うことといえるかもしれません。感動したり、ドキッとしたり、勇気づけられたり。自分の言葉を発信したり、誰かの言葉を読んだり聞いたりすることは、そんな思いもよらないコミュニケーションの連続です。
自分の言葉を誰かに届けることに挑戦し、その不思議さの糸口を全身で体感した子どもたち。大人も子どもも一緒になって机を囲んだこの日の経験が、彼らがこれから言葉を携えて生きる上で迷いや戸惑いを感じた時、少しでも彼らを勇気づける記憶になれていたら嬉しく思います。

最後に、本プログラムの企画・実施にあたり、TSURUMIこどもホスピス職員の川戸大智さん、青儀祐斗さんをはじめ、たくさんの方々にご尽力をいただきました。FabCafe Kyotoへのデジタルスクリーン製版機導入から主にテクニカル面でのサポートをいただいている株式会社色素オオタ・オータスさん、昨年度に続いてのご協力となる京都産業大学情報理工学部の伊藤慎一郎教諭、そして京都市立芸術大学で教鞭を執る桑田知明さん、楠麻耶さんと、両大学に加え京都芸術大学から参加を希望してくれた学生・卒業生の中村心音さん、高木祐輝さん、村上きららさん、小幡咲奈さんへ、この場を借りてお礼申し上げます。
本年度は、FabCafe Kyotoを通じて出会った上述の福祉・デジタルファブリケーションの領域で活動されている皆さまへ企画の立ち上がり段階からお声がけを行うことで、より多面的な視点からプログラムを設計することができました。また実施当日、子どもたちが主体的に場に関わるムードが醸成できたのは、学生メンバー皆さんの「つくることの楽しさ」に主軸を置いた、フラットな姿勢でのコミュニケーションがあったからこそでした。
ものづくりを志す学生や、機材のノウハウを持つメーカーなどの企業、そして福祉の現場であるTSURUMIこどもホスピス。私たちは、彼らがともに気づきや学びを共有しながら、「つくる」ためのより多様な機会の開き方を実践できる場へと、本取り組みが醸成されることを目指しています。

イベントレポートのご案内
TSURUMIこどもホスピスwebサイトにて、スタッフの川戸大智さんによる本イベントのレポート記事が公開されています。本レポートではご紹介しきれなかった当日の詳しい工程やワークショップの意図などを分かりやすくまとめていただいておりますので、ぜひこちらも併せてご一読ください。
-
山月 智浩
FabCafe Kyoto ディレクター
1998年大阪府生まれ、2021年京都芸術大学空間演出デザイン学科卒業。2022年2月よりFabCafe Kyotoに参画。 「Fab」の文脈を人文学的なアプローチで解釈し、誰もが持つ「つくる」力を引き出すためのプログラム設計に繋げることを得意とする。ワークショップや展示、トークイベント等の企画や店舗の情報発信を通して、生産や消費に性急な社会をやわらかくほぐすための実践に励む。人が感化し合い有機的なムードが醸成される場のあり方に関心を向け、個人でもフォトグラファーとして活動中。年に一度、野外鍋を敢行する。
1998年大阪府生まれ、2021年京都芸術大学空間演出デザイン学科卒業。2022年2月よりFabCafe Kyotoに参画。 「Fab」の文脈を人文学的なアプローチで解釈し、誰もが持つ「つくる」力を引き出すためのプログラム設計に繋げることを得意とする。ワークショップや展示、トークイベント等の企画や店舗の情報発信を通して、生産や消費に性急な社会をやわらかくほぐすための実践に励む。人が感化し合い有機的なムードが醸成される場のあり方に関心を向け、個人でもフォトグラファーとして活動中。年に一度、野外鍋を敢行する。